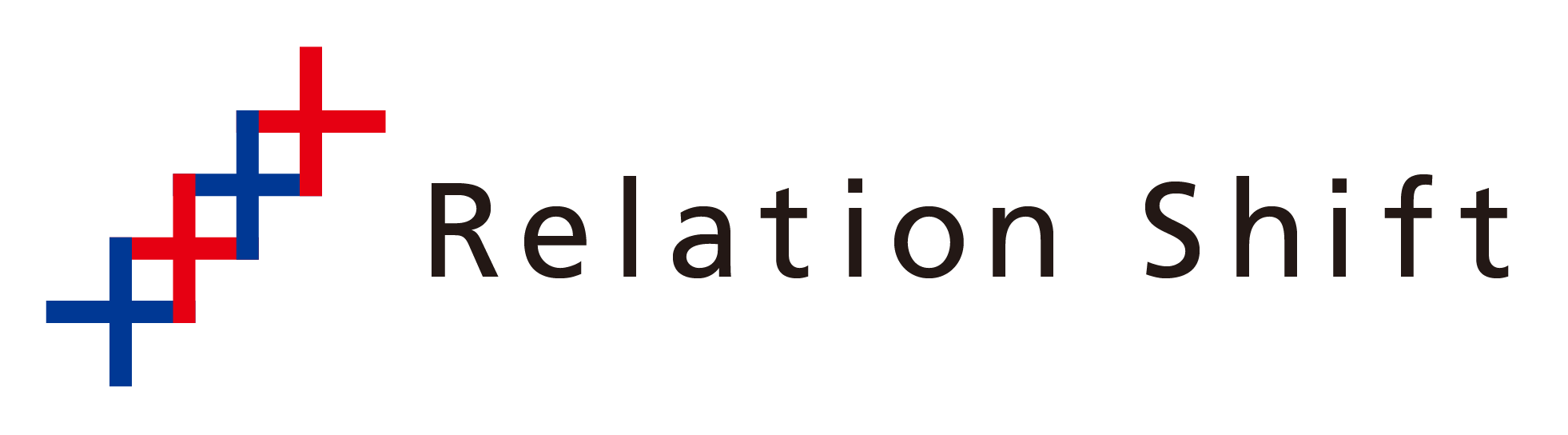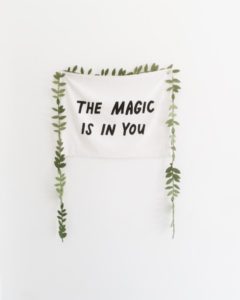イノベーションって実はシンプル
こんにちは、ヨシケンです。
イノベーション、イノベーション、昨今企業では
聞き飽きるくらいに叫ばれるNo1ワード「イノベーション」
ネットでもイノベーションと検索すれば「どうすればイノベーションが起きるのか?」
の記事が乱立しています。
そこで今回は、イノベーションはなぜ起きづらいのか?について考察してみました。
ではいつものように「イノベーション」の定義から確認していきましょう。
イノベーション(英: innovation)とは、物事の「新結合」「新機軸」「新しい切り口」「新しい捉え方」「新しい活用法」(を創造する行為)のこと。一般には新しい技術の発明を指すと誤解されているが、それだけでなく新しいアイデアから社会的意義のある新たな価値を創造し、社会的に大きな変化をもたらす自発的な人・組織・社会の幅広い変革を意味する。つまり、それまでのモノ・仕組みなどに対して全く新しい技術や考え方を取り入れて新たな価値を生み出して社会的に大きな変化を起こすことを指す。
かなり広義に渡りますね。
ポイントは、「新しい価値の創造」と「社会変革」というところですね。
「社会変革」は、新しい価値の創造によるものなのでまず何よりも「新しい価値の創造」
が必要になってきますね。
まー当たり前といえば当たり前の話です。
しかし、ここが最も難しいポイントではないでしょうか?
そもそも新しい価値をどう創造するの?って。
昨今企業もこの新しい価値の創造は、自社だけでは難しいということで
「オープンイノベーション」を開始しました。

オープンイノベーションの現状
オープンイノベーションとは自社だけでなく他社や大学、地方自治体、社会起業家など異業種、異分野が持つ技術やアイデア、サービス、ノウハウ、データ、知識などを組み合わせ、革新的なビジネスモデル、研究成果、製品開発、サービス開発、組織改革、行政改革、地域活性化、ソーシャルイノベーション等につなげるイノベーションの方法論です。
オープンイノベーションは方法論として素晴らしいと思います。
しかし、いかがでしょうか?オープンイノベーションによって生まれたイノベーションって聞いたことありますか?
いくつか事例はあるそうですが、思うような結果を出せていないのが現状ではないでしょうか。
半年ほど前、あるイノベーションのイベントで大手メーカーのオープンイノベーション担当の方二名とお話する機会がありました。
お二人ともオープンイノベーションで、なかなかイノベーションが起こせないということに問題意識をもって参加されていたのですが、話していくうちにそれぞれの会社が考えるオープンイノベーションとは何か?という話になったんです。
そこでの回答が両社とも「我社のサスティナブルな存続」だったんです。
あれ?オープンじゃなくてそれってクローズじゃない?、お二人とも苦笑していました。
結局、オープンイノベーションによってイノベーションが起きないのは、オープンじゃないからっていかがですか?
本末転倒ですよね。
でもコレこそがまさにイノベーションが起きない最大の原因なんです。

「オープン」、「クローズ」とは何か?
イノベーションはそもそも「オープン」が原則になければ起きません。
なぜなら、「新しさ」とは「クローズ(いままでの概念)」の中には生まれないからです。
それなら「オープン」になればいいじゃないか?と思いますよね。
でも出来ない。事例にあった企業もそんな事はわかっています。
ではなぜ、出来ないのでしょうか?
そこには2つの大きな原因があります。
1つは、そもそも「クローズ」自体を規定できていないということです。
もう1つは「クローズ」の状態を手放す勇気がないこと。
「クローズ」自体を定義できなければ「オープン」が何か?がわかりません。
企業で「クローズ」とはすなわち、我社とは何か?を規定することです。
我が社の存在を規定することとも言えます。
組織は個人の集合体ですので、結局最小単位では個人のイノベーションが
必要となってきます。
個人のレベルでは「自分とは何か?」、「自分とはどんな存在か?」を
規定することになります。
「クローズ」が規定できて初めて、「クローズ以外=オープン」が選択できます。
あとは、2つ目に上げた「クローズ」を手放し「オープン」を選択する勇気だけです。
※勇気に関してはまた別記事でお話したいと思います
では「クローズ」をどうしたら規定できるのでしょうか?
まずは我々のストーリーを通して、実際に私がどうやって自分の規定を発見していったのか
を体験してみてください。
自分の規定を発見し、勇気を持って手放すことで新しい人生を歩んでみませんか?
自分のイノベーションを起こしたい、そんな人をお待ちしています。